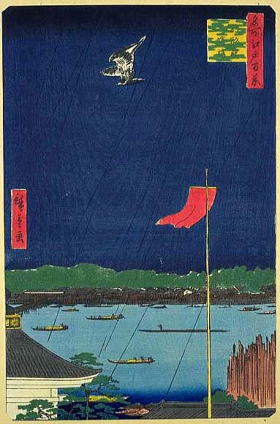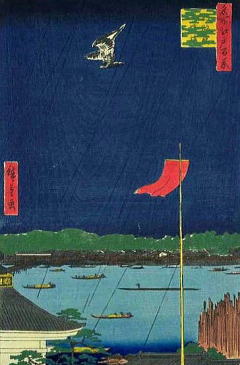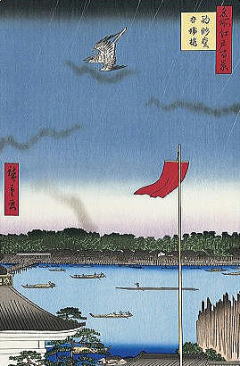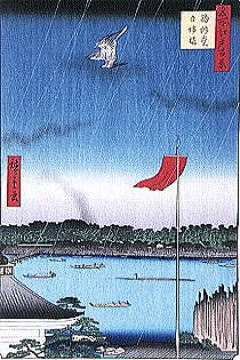| 深夜「トッキョキョカキョク トッキョキョカキョク」けたたましい鳥の鳴き声に夢を破られ時計を見ると,23時43分を指していた。ホトトギスが渡って来たようだ。 佐々木信綱作詞による小学唱歌「夏は来ぬ」に♪忍音(しのびね)もらす♪のフレーズがある。これは初夏,南の国から渡ってきたホトトギスの初音のことで,なかなか情緒のある言葉だが,私が聞いたこの夜の忍音は,情緒とはほど遠い鳴き声だった。 ホトトギスはツバメやオオルリと同じ夏鳥で 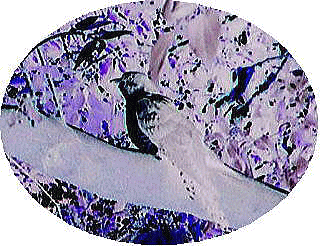 夜遊びが好きな鳥のようで,2年前,久しぶりに旧友と痛飲,真夜中の午前1時頃,浦賀駅から30分ほどの道のりをフラフラ歩いて帰宅途中,「トッキョキョカキョク トッキョキョカキョク」の鳴き声を聞いたことがある。 その上,ホトトギスは無責任な鳥で,卵はウグイスの巣に産み,子育てはウグイスに任せ繁殖する托卵性がある。観音崎にはウグイスが多いので,育て親を捜すのに苦労しないのか,卵を産むと夜昼の見境なく遊び回っている。最近は人間にもこのような手合いが増えているようで,そのような親たちに”ホトトギス族”の名称を贈呈したいと思うがいかがなものだろう? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005.5.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.6.8掲示板に“ぶせふ”さんから下記のようなコメントを頂いた。 ホトトギスの声を気持ちよく聞かせていただきました。実は、今日木曽川周辺で実際に聞いてきたところで、改めて、自然のすばらしさを味わったところです。 さて、目には青葉山ホトトギス初鰹の句は、正岡子規の句ではなくて、山口素堂の句です。もう、ご承知になられているかもしれませんが、つい指摘させていただきたくなりました。ごめんなさい。 私が俳句の作者を正岡子規としたのは,ある新聞のコラムでそのように書かれていたのを見て,そうだったのか!と思いこんだのが原因。調べ直してみると,紛れもなくご指摘の通り。このページをご覧になって,そのように思いこんでいる方が居るとすれば,本当に申し訳ない気持ちです。「ごめんなさい」は,私が言うべき言葉ですね!“ぶせふ”さん,ご指摘ありがとうございました。 今回,句の作者を確認する過程で,幾つか興味深い事実を知った。 ☆正岡子規は結核で喀血後,「鳴いて血を吐くホトトギス」になぞらえて「子規」と号した。 「子規」とはホトトギスの漢語的表現の一つ。 ☆「鳴いて血を吐くホトトギス」を子規の俳句という説もあるが疑問? 俳句ならば上の句がある筈なのに存在しない?諸説入り乱れて混沌としている。 ☆俳誌「ホトトギス」は正岡子規,高濱虚子等によって創刊された。 このように,正岡子規とホトトギスは非常に密接な関係にある。新聞のコラム担当者は,これらの関係を知りすぎていて,「目には青葉山ほととぎす初鰹」の作者を子規と勘違いされたのだろう。 忍音を聞いて以来,ここ2週間。ほぼ毎日,昼夜を問わずホトトギスの鳴き声を聞く。真夜中に聞く甲高い鳴き声は「鳴いて血を吐くホトトギス」を連想させ,あまり気持ちの良いものではない。そのくせ,たまに鳴き声を聞かないと,どうしたのだろうか?と心配になる。本当に奇妙で不思議な魅力のある鳥だ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 小学唱歌「夏は来ぬ」の出だしに♪卯の花の,匂う垣根に♪のフレーズがある。卯の花はウツギの別名で空木と書き,茎が中空なことに由来する。白い花の咲く時期が5月中旬から6中旬。ホトトギスが南方から渡来して,忍び音をもらす時期とほぼ重なるため,作詞の佐々木信綱はそう表現したようだ。それにしても,いささか高級な文学的表現?で,私は子どもの頃,言葉の意味など全く理解せずに,夏が来たのがただ嬉しくて,口ずさんでいたように思う。 | |
 2011.5.24 |
|
 2011.5.23 |
|